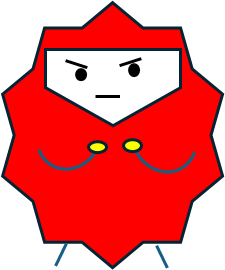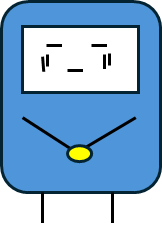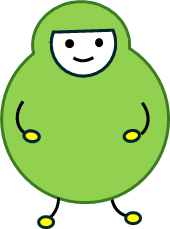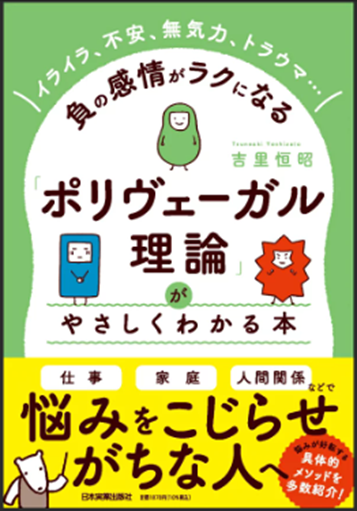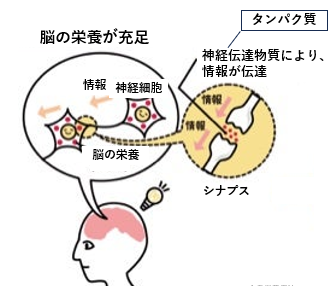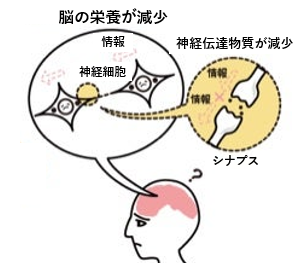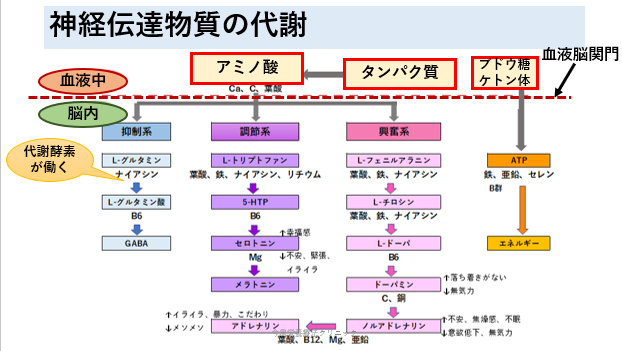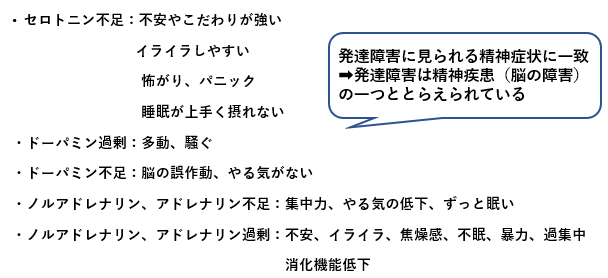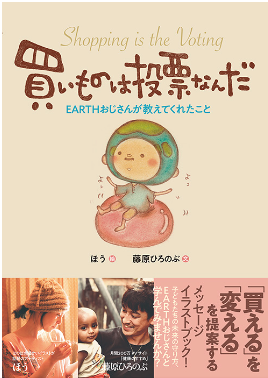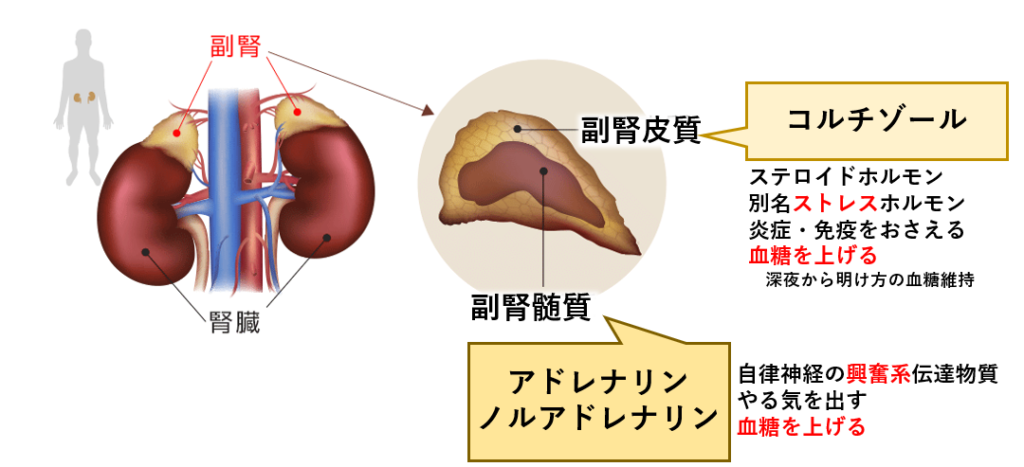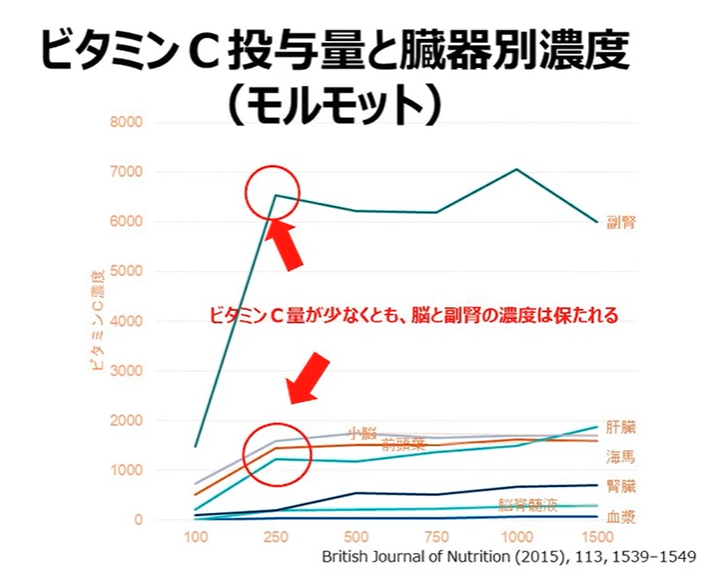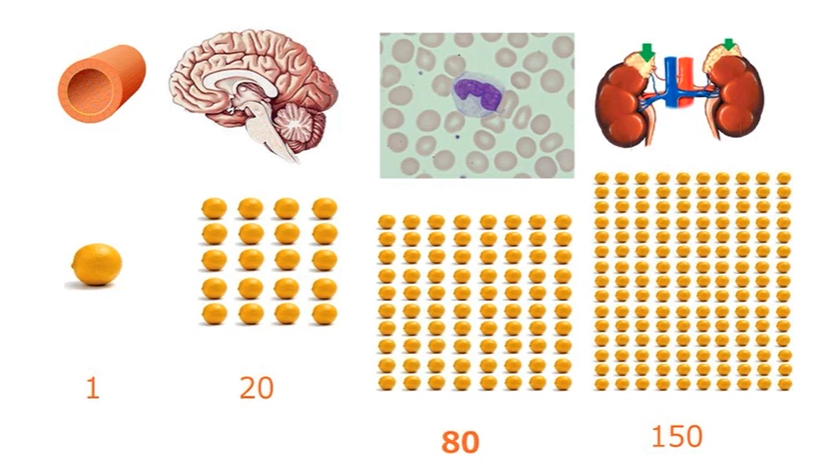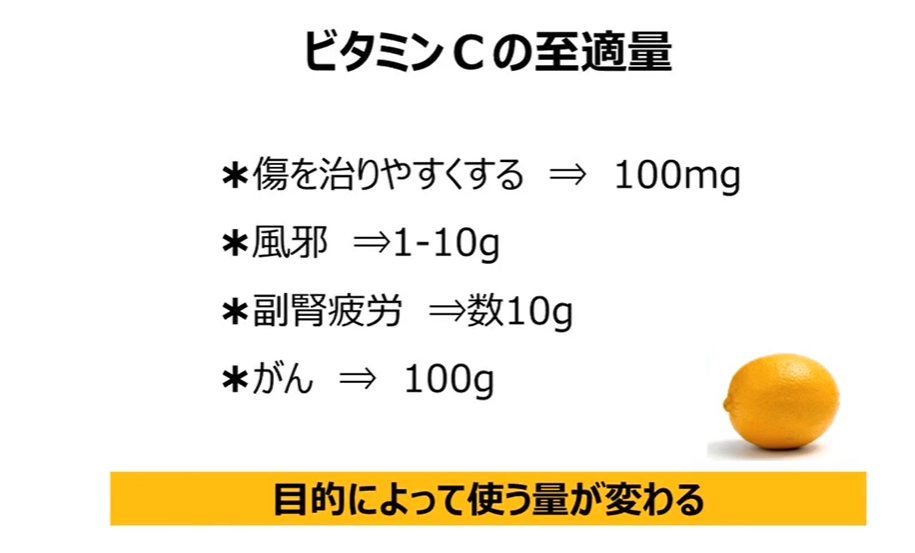緑を増やすツールやエクササイズをご紹介しましょう。

リラックスアロマ
①ラベンダー ②イランイラン ③オレンジスイート
④ネロリ ⑤ベルガモット ⑥ペパーミント など、
「好き」な香りを
・簡単なアロマの使い方
<芳香浴>就寝時の枕元、仕事中のデスク付近、玄関の靴箱の中
①精油を、ティッシュペーパーやハンカチに1~2滴含ませます。
②マグカップに熱湯をはり、精油を1〜2滴
③芳香拡散器を使う
<フットバス>
・洗面器に40~42度ほどのお湯をはり、アロマオイルを1~3滴落として
15分ほど足をつける→出る、をリラックスした姿勢で繰り返します。

体を温める
冷えると体温を逃がさないため血管が収縮=交感神経が緊張
熱を生み出すために余分なエネルギーを消耗
➡温かい下着・上着、温かい飲み物(カフェインNG)、
ひざ掛け、電気毛布
低血糖は「緑」の敵
血糖を上げるために交感神経優位になりやすくなります。
マインドフルネス
「今ここ」に存在する、心をこめるもの(中心対象)を決め、そこに意識を集中する。
呼吸、食事、身体を触る、ストレッチなど身近なもの、なんでもよいですが、
過去・未来のことは考えず、「今ここ」に集中することが重要です。
難しく思われる方は、深~い深呼吸をして、自分の呼吸のみに意識を集中してみましょう!
あいうべ体操:顔と舌に刺激

「鼻うがい」「喉のうがい」「歯磨き」「顔に刺激」
揺らぎをヒントにしたエクササイズ スワイショウ

骨盤を左右に回転
共に動く両腕が胴体に巻き付いてくる感じ
両腕を肩の高さまで上げ、重力に委ねるように落とす
その反動で体の後ろまで両腕が動く
おろした腕の反動で、また両腕を肩の高さまで上げ、この動作を繰り返す
腕を左右交互に前に伸ばす
肋骨周りの力みが取れる感覚を味わう
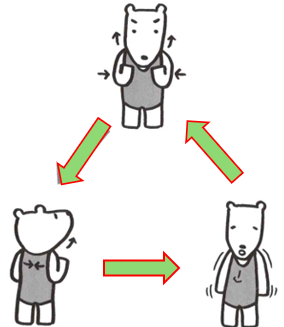
筋弛緩法:緊張と弛緩の揺らぎ
①両腕を前に出してこぶしを握り、前腕の筋肉の緊張を感じる
②肘を曲げ、こぶしを肩の方に近づけ上腕に力を入れる
③肩を上げたまま慮こぶしを左右に開き、胸を開く
④3~5秒緊張させた後に一気に全ての筋肉を脱力させる
暖かくなる感じ、、シュワ―っとなる感覚などを味わう
自然の中の揺らぎ
緑は柔軟性があります。二者択一ではなくゼロヒャク思考でもない、つまり揺らぎです。
(優柔不断とは、違うよ)
身近にも揺らぎがたくさんあります。
波打ち際に打ち寄せる波
草木の葉っぱが揺れるようす
水面に反射する太陽(月)の光
ロウソクの炎
適度に揺れる楽器の音色
赤ちゃんが抱っこされてゆらゆら
タッチの効用 肌と肌が優しく触れあっている(緑の手)
ただそっと手を添える、 なでなでとさする、 手のぬくもりで温める
覆い包む、 ぎゅっと握る、 揉む、 揺するタッピング
合掌もタッチの効用の一つです

セルフハグ・バタフライハグ
<セルフハグ>
右手で左肩を触れ、左手で右肩を触れる。
自分で心地よい場所・強さを見つける
<バタフライハグ>
セルフハグの形で、手や指のタッピング
心地よいスピード、リズムを見つける
どうしても難しい時は「問題」から一旦離れよう
「問題」から一旦離れると、「問題」を冷静に見ることができるようになり、
相手を変えて安心する「赤モード」から、自己調整を優先する「緑モード」になりやすくなります。
そして、「赤モード」や「青モード」に、緑をブレンドする事を意識しましょう!
「ポリヴェーガル理論」「ブレンド」を語れる仲間を増やす
ポリ語で話せる仲間が増えると、人間関係がきっと楽しくなります。
ぜひ、ポリ仲間を増やして人生を楽しみましょう!!!